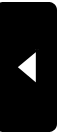2009年11月27日
プロジェクト研究結果発表会
今日は2009年度における6部門で取り組んできたプロジェクト研究の発表会の日でした。午後からの時間を使って、各部門10分程度の発表を養鶏部から始めて、最後に養豚部の発表で終わりました。

養鶏部は「おがくず発酵飼料の研究」をプロジェクトテーマに、これまで取り組んできた、おからサイレージ以外にも廃棄物として捨てられている資源を有効利用していきたいという生徒の強い思いからスタートしてきました。今はまだ、結論づけた答えは出せませんが、飼料の経費削減や、国産自給飼料の割合が向上するなどのことを考えると、今後の産卵成績に期待したいところです。

果樹部は「キウイの受粉における花粉増量剤の検討」をテーマにキウイの有機栽培技術を模索してきました。従来花粉増量剤として使ってきた染色石松子が有機栽培の範疇から外れたことで、新たな増量剤として炭粉やコンスターチ、片栗粉、黒鉛入り石松子などを試したようです。結果としてもまずまずのデータが取れたようで、これからもよりキウイの生産に適した安心安全な資材で、キウイを栽培していって欲しいなと思います。

作物部は「ヒメイワダレソウによる抑草効果」をテーマとし、畦草を抑草することで、除草作業への労力や作業経費の削減を計るというものでした。ヒメイワダレソウは、栄養繁殖することから、最初の初期投資に経費がかかってしまうものの、その後の繁殖に関しては、経費をかけずにできるということです。これからの繁殖に要する手入れなどの労力なんかをこれからの課題としていく模様です。

酪農部の「育成牛の放牧飼育+(サイレージ作り)」は、土地の有効利用と飼料費の削減、そして育成牛の肢蹄強化を目的にしていました。結果は、どの育成牛とも順調な生育がみられたことからも、まずまずの結果であったといえるのではないでしょうか。また、サブプロジェクトとして今年から復活した、地域との連携ともいえる、河川敷の葦のサイレージ化についても、保存方法に課題はあるものの、牛のよく食べる高品質のサイレージができたようです。

野菜部は「自然農薬による病害虫対策の確立」をテーマに、五種の自然農薬を選抜しトマトに散布、アブラムシの繁殖をいかにして抑えるかということに挑戦したようです。結果、五種の自然農薬における効果は、期待できず、今回のプロジェクトからは良い結果は得られなかったように思います。しかし、プロジェクト中のビニールハウスの中にいる、アブラムシの天敵であるアブラバチの存在に気が付き、これから天敵の導入についても考えていく必要があると思います。

養豚部は、「完全無添加の手作りソーセージ&ハムベーコン加工販売」ということで、何度もオリジナルソーセージの試作をしたようです。養鶏部の卵や野菜部のニンジンやトマトなど愛農で取れるものを使ったソーセージ作り、今もなお継続し試作中とのこと。愛農らしいおいしいソーセージが完成するよう期待したいです。

養鶏部は「おがくず発酵飼料の研究」をプロジェクトテーマに、これまで取り組んできた、おからサイレージ以外にも廃棄物として捨てられている資源を有効利用していきたいという生徒の強い思いからスタートしてきました。今はまだ、結論づけた答えは出せませんが、飼料の経費削減や、国産自給飼料の割合が向上するなどのことを考えると、今後の産卵成績に期待したいところです。
果樹部は「キウイの受粉における花粉増量剤の検討」をテーマにキウイの有機栽培技術を模索してきました。従来花粉増量剤として使ってきた染色石松子が有機栽培の範疇から外れたことで、新たな増量剤として炭粉やコンスターチ、片栗粉、黒鉛入り石松子などを試したようです。結果としてもまずまずのデータが取れたようで、これからもよりキウイの生産に適した安心安全な資材で、キウイを栽培していって欲しいなと思います。
作物部は「ヒメイワダレソウによる抑草効果」をテーマとし、畦草を抑草することで、除草作業への労力や作業経費の削減を計るというものでした。ヒメイワダレソウは、栄養繁殖することから、最初の初期投資に経費がかかってしまうものの、その後の繁殖に関しては、経費をかけずにできるということです。これからの繁殖に要する手入れなどの労力なんかをこれからの課題としていく模様です。
酪農部の「育成牛の放牧飼育+(サイレージ作り)」は、土地の有効利用と飼料費の削減、そして育成牛の肢蹄強化を目的にしていました。結果は、どの育成牛とも順調な生育がみられたことからも、まずまずの結果であったといえるのではないでしょうか。また、サブプロジェクトとして今年から復活した、地域との連携ともいえる、河川敷の葦のサイレージ化についても、保存方法に課題はあるものの、牛のよく食べる高品質のサイレージができたようです。
野菜部は「自然農薬による病害虫対策の確立」をテーマに、五種の自然農薬を選抜しトマトに散布、アブラムシの繁殖をいかにして抑えるかということに挑戦したようです。結果、五種の自然農薬における効果は、期待できず、今回のプロジェクトからは良い結果は得られなかったように思います。しかし、プロジェクト中のビニールハウスの中にいる、アブラムシの天敵であるアブラバチの存在に気が付き、これから天敵の導入についても考えていく必要があると思います。
養豚部は、「完全無添加の手作りソーセージ&ハムベーコン加工販売」ということで、何度もオリジナルソーセージの試作をしたようです。養鶏部の卵や野菜部のニンジンやトマトなど愛農で取れるものを使ったソーセージ作り、今もなお継続し試作中とのこと。愛農らしいおいしいソーセージが完成するよう期待したいです。
[三野]
Posted by 愛農高校 at 18:20│Comments(2)
│農業クラブ
この記事へのコメント
田んぼの畦草対策は大変重要な作業です
草刈作業は高温期の重労働で、ほっとくわけには行きません
ヒメイワダレソウの成果が期待されます
似た植物に「ヒメツルソバ」というのもありまして、私は来年から取り入れるつもりです
これは寒さに強く今でも花を咲かせています
愛農のヒメイワダレソウの今はどの様な姿ですか、
草刈作業は高温期の重労働で、ほっとくわけには行きません
ヒメイワダレソウの成果が期待されます
似た植物に「ヒメツルソバ」というのもありまして、私は来年から取り入れるつもりです
これは寒さに強く今でも花を咲かせています
愛農のヒメイワダレソウの今はどの様な姿ですか、
Posted by 三船進太郎 at 2009年12月02日 19:15
コメントありがとうございます。「ヒメツルソバ」、耐寒性が高いようでいいですね。現在のヒメイワダレソウは、地表に近い細かい葉を中心に、まだ緑色をしています。花は、秋口に散ってから全くない状態です。ヒメイワダレソウはそれほど寒さに強くないようですので、今後地上部は枯れていくのではないかと思います。草刈り、本当に時間がかかるので、少しずつでも軽減していきたいです。
Posted by 愛農高校 at 2009年12月05日 10:57
at 2009年12月05日 10:57
 at 2009年12月05日 10:57
at 2009年12月05日 10:57※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。